サムネはTwilight Solitudeからお借りしました。
挨拶
皆さん、お初にお目にかかります。しゃまと申します。 本プロジェクトにプロジェクト補佐という役割で関わらせていただいている甲殻類です。

メゾン荘 201号室をお借りさせていただきました。
主にゲームシステム・ルールの整備、シナリオの案出し、情報整理等で関わっています。VRCに関してはまだまだ初心者ですが、精一杯頑張らせていただく所存です。 よろしくお願いします。
本記事ではまず私が何をしている人なのかをお伝えします。そしてゲームが持つ教育性に対する考えと、本プロジェクトに対しての思いを伝えていきたいと思います。 拙文となりますが、最後までお付き合いいただけますと幸いです。
何してる人なの?
大学の教育ゲーム研究チームメンバーとして、教育的なアプローチとゲーム性の両立を目指し、すごろく型アナログ学習ゲームの開発に携わってきました。
開発現場ではゲームの企画・実装を一から行い、UI設計、プレイバランスの調整等を担当しました。 また、超異分野学会で該当ゲームの展示をさせていただきました。発表用のポスター作成や、展示対応の業務にも基本的に一人で取り組み、当日は多数の来場者との対話を通して学びの価値を伝える機会を得ました。 その後も、ゲーム展示イベントや産学連携の場にて展示を行い、海外の参加者や企業関係者の方との交流を通して、多様な視点と反応を得る貴重な経験を積んでいます。 現在はこの経験を活かし、教育と遊びが交差する場づくりを模索しつつ、本プロジェクトにも貢献できればと考えています。

メゾン荘 201号室をお借りさせていただきました。
ゲームが持つ教育性
ゲームはしばしば、勉強の敵とされます。ゲームをするくらいなら勉強をするべきだ、ペンと紙を持って黙々と努めなさい、と。しかし、実はゲームって、勉強に非常に適した媒体なんです。ここで、ゲームってそもそもなんなんだろう、と立ち返ってみましょう。
ゲームにはまず、なにかしらの「目標」が必要です。この目標はしばしばプレイヤーに委ねられますが、ほとんどのゲームでは開発者側が与えます。例えば、RPG。魔王を倒したり、世界を救ったり。作品によって様々ですが、必ず目標がありますね。プレイヤーはこの「目標」を達成しようとして、初めてゲームをプレイします。
そして、「報酬」。これもゲームには必要不可欠です。プレイヤーが設定する場合を除いて、開発側が定めます。RPGならレベルが上がって敵を倒しやすくなるだとか、ストーリーを進めることができる、等が当てはまるでしょう。
他にも「ルール」や「挑戦性」、「競争性/協調性」など様々な要素がありますが、少なくとも「目標」と「報酬」が存在することで、プレイヤーは自らの行動に意味を見出し、ゲームプレイに動機を持つことができます。
この構造は、過去から現在にかけて数多くのゲームで受け継がれており、人の脳にとって非常に“クリティカル”な設計なのです。 言い換えれば、ゲームは脳の報酬系を絶妙に刺激するよう設計されている媒体であり、それゆえに私たちは自然と夢中になってしまう。
この構造を勉強に応用したら皆が楽しく学べる、最強の教育法が生まれるのでは—私は、そう考えます。
プロジェクトに対して
本プロジェクトでは四次元をあらゆる感覚から体験することで、プレイした人の四次元への興味を引き出し、より身近に四次元を感じてもらう事ができると期待されます。また同時に、四次元だけでなくVRも体感できます。これは人類の視野を広げ、新たなアイデアの芽を育てます。アイデアの芽は未来という名の葉を作り、やがて繁栄の実を垂らすでしょう。
私はその芽を、葉を、実を見たい。そう思い、このプロジェクトに参加しました。できることはそう多くはないかもしれませんが、少しでも芽が植わるように。
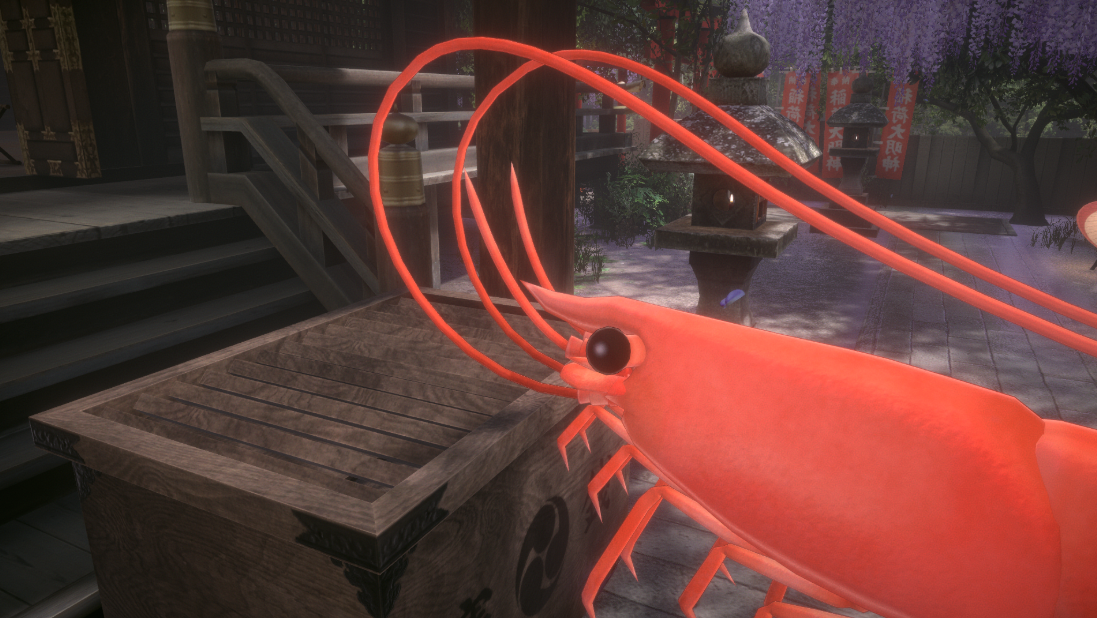
Japan Shrineをお借りさせていただきました。
